「うつ病」という病気が世に知られるようになって久しいですが、近年ではそのうつ病の中にもさまざまなタイプが存在するということが知られています。
そのうちの一つが「仮面うつ病」といわれるものです。
この仮面うつ病の性質としては、通常のうつ病とは違い、身体面での症状が精神面より優先して表面化するということが挙げられます。
そのため仮面うつ病は患者自身においてうつ病として自覚がなされにくく、誤診なども多いということが言われています。
そこで今回は、この仮面うつ病の症状・原因・対処法に対する知識についてまとめてお伝えします。
もし現在、ご自身や知人に心配な点がある方は参考にしてみて、症状を感じた場合は病態が悪化する前に早めに対処法を実践してみてください。
仮面うつ病の知識まとめ、症状・原因・対処法
仮面うつ病の症状8選
自律神経の不調
仮面うつ病の症状として最も多いものに、自律神経の不調が挙げられます。
自律神経とは身体を緊張、あるいは興奮させる交感神経と、リラックスさせる副交感神経の2つから成り立つのですが、このバランスが崩れることによって、
・動悸や息切れ
・めまい
・気温が低いのに汗をかく
・気温が高いのに寒気を感じる
などの症状が現れます。
自律神経の不調は一般的に自立神経失調症という病名で呼ばれるのですが、仮面うつ病はこの病気と混同され、誤診をされたり、あるいは本当に併発をしていたりする場合が多いといわれています。
消化器系症状
何か嫌なことがあった際に、突然腹痛が起こったという経験があるという人は少なくないのではないでしょうか。
消化器官、特に腸は「第二の脳」と呼ばれるほどに複雑な神経伝達回路を有しているとされ、ストレスからの影響も受けやすいといわれています。
そのようなこともあり、仮面うつ病による身体症状は消化器官にて起こりやすいという傾向があります。
具体的な症状としては腹痛や下痢、便秘、腹部不快感などが挙げられます。
慢性的に腸が不調を起こす病気として過敏性腸症候群(IBS)というものがありますが、この病気はほとんどがストレスなどの心因性であるとされ、うつ病とも深い関係があるとされています。
呼吸障害
仮面うつ病の身体症状としては、過呼吸や呼吸困難などの呼吸障害が発生する場合があります。
こうした呼吸障害を生じる精神疾患としてパニック障害がよく知られていますが、この病気はうつ病とも大変関連が深く、併発することも珍しくはありません。
耳鳴り
耳鳴りの原因として考えられる代表的な病気としてあげられるのがメニエール症候群です。
メニエール症候群は内リンパ水腫ともいわれ、リンパが水ぶくれのように腫れることによって発生します。
仮面うつ病の場合にもこの耳鳴り症状は頻繁に発生するのですが、こうしたことからメニエール症候群は仮面うつ病との間で誤診を生じやすい病気であると言われています。
ただし、仮面うつ病とメニエール症候群はどちらもストレスを原因としているため、併発をする例も存在します。
物忘れ
仮面うつ病以外のうつ病全般の傾向として「物忘れが激しくなる」ということがあるのですが、仮面うつ病は心的症状があまり表面化しない特徴を持っているため、物忘れを引き起こす代表的な病気である認知症と疑われるケースもあります。
特に高齢者のうつ病の場合はこうした誤診や混同が生じることも珍しくありません。
ただしその一方でうつ病とアルツハイマー型認知症との間には何らかの関連性があるとの見方もあり、若いころうつ病を発症した人は老年期に入り認知症を発症する割合が大きいという統計結果も存在します。
微熱
仮面うつ病の身体症状として、微熱を生じ、その熱がなかなか下がらないという場合もあります。
うつ病において微熱が生じる原因としては、セロトニンの不足が原因として挙げられます。
脳内物質の一種であるセロトニンは、身体をリラックスさせると同時に体温を調整する役割を担っているのですが、この分泌が不足することにより体温調節が不能となり、結果として身体の熱が下がらなくなるのです。
性機能障害
仮面うつ病以外にもうつ病全般の症状として勃起不全(ED)や生理不順などは珍しくありませんが、仮面性うつ病の場合には心的症状を伴わず、これらの性機能障害のみが表面化する場合があります。
また、既にうつ病を患っているという人の場合、抗うつ剤(SSRI)の副作用として性機能障害が発生する場合もあります。
思考障害・不眠
「考えがまとまらない」「物事に関心が持てない」などの思考障害や、「夜眠れない」などの睡眠障害は、仮面うつ病以外にもうつ病全般に広く見られる症状です。
しかし実際にはうつ病を発症している患者がうつ病を自覚しないままに内科や神経内科などに来院し、その後うつ病との診断が下される場合もあります。
仮面うつ病の原因3選
性格
仮面うつ病に限らず、うつ病全般の最も直接的な原因としては性格因子が挙げられます。
うつ病にかかりやすい性格としては
・秩序や規則を重視する
・完璧主義である
・言いたいことが言えない
・悲観的、被害妄想に陥りやすい
などが挙げられますが、さらにうつ病の中でも仮面うつ病になりやすい性格としては、
・自分に厳しい
・面子や見栄を重視する
が挙げられています。
このような人々は自分自身の精神的な弱さを自覚できず、実際にはうつ病の症状が出ているにもかかわらず、それを無意識的に否認してしまう傾向があるとされます。
また人間の性格は生い立ちや現在の境遇などの「環境因子」と、親や先祖から受け継いだ「遺伝因子」によって成り立つのですが、この内家族親族などにうつ病患者や自殺者などがいる場合、うつ病にかかりやすい遺伝的特性が性格に受け継がれるということがあります。
何らかの出来事
進学や就職・転職、事件や事故、災害、自分や身近な人の不幸など、何らかの出来事をきっかけとして仮面うつ病を発症するという場合もあります。
これらの中でも、特に事件や事故、災害、あるいは戦争などの結果として起こるものを、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と言います。
PTSDとは、強烈なショック体験や強い精神的ストレスが心のダメージとなり、時間がたってからもその経験に対して強い恐怖を感じるものです。
PTSDによって仮面うつ病を発症した場合、患者本人は自分自身の心的ダメージを自覚できず、処置を取ろうとしない場合もあり、重症化をしやすいとも言われています。
さまざまなストレス
その他日常におけるさまざまなストレスが蓄積することにより、ある日突如として仮面うつ病を発症するという場合もあります。
この際受けるストレスの大きさやそのパターンなどは人によって千差万別であり、うつ状態の深刻度もさまざまです。
仮面うつ病の対処法5選
薬物療法
仮面うつ病に限らず、うつ病全般の対処法として最もオーソドックスなのが薬物療法です。
ただし特に仮面うつ病の場合にはまず身体症状が顕在化をするという性質上、通常の抗うつ剤であるデパス、パキシル、ドグマチールやSSRIなどに加え、身体症状を抑えるための薬が処方される場合もあります。
具体的には睡眠障害があるという場合には、前述の抗うつ剤に加え睡眠薬などが処方されたり、消化器官の症状があるという場合には抗うつ剤と胃腸薬が処方されます。
またその他に、これら薬の副作用を抑えるための薬が加えて処方される場合もあります。
カウンセリング
薬物療法と並び、うつ病の治療としてオーソドックスなのがカウンセリングです。
歴史的には抗うつ剤の研究が本格化したのは第二次世界大戦後であり、それ以前にはうつ病治療はカウンセリングかもしくは電気ショックが主となっておりました。
うつ病のカウンセリングの種類としては、
・簡易的に患者の話を聞くというものから過去のトラウマの治癒を目的とした精神分析療法
・家族や友人、あるいは治療者との間で良好な人間関係を築くことで傷を癒やそうとする家族療法
・行動パターンを変化させることで抑うつ的な思考に変化をもたらそうとする行動療法
・物事に関する認知パターンを変化させていこうとする認知療法
などがあります。
鍼灸治療
神経や所謂「ツボ」を刺激することにより、神経ネットワークの働きの産物である精神状態にも変化をもたらそうとするのが鍼灸治療です。
仮面うつ病の、特に自律神経失調症に近い身体症状が出ている場合にはこの治療法が有効であるとされています。
漢方療法
漢方療法も、特に自立神経失調症に近い症状の仮面うつ病に関しては有効であるとされています。
また漢方にはさまざまな種類があるのですが、その中には不眠や消化器官の不調などに効果を持つものも多く存在します。
仮面うつ病に対して効果を持つ漢方としては、
・柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
・柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)
・抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
などがあります。
食べ物を変える
これは仮面うつ病に対する「対処法」というよりは「予防法」に近いのですが、日常的に摂取する食べ物に気をつけ、改善をしていくことで精神状態を良好に保つというものです。
例えば糖分を過剰に摂取した場合、インスリンが過剰に分泌されるために血糖値が下がるのですが、人間の脳は低血糖状態ではノルアドレナリンを分泌しやすくなり、それによって不安感などが生じやすくなります。
また肉類などを摂り過ぎ、腸内に悪玉菌が増加するようになるということも精神状態悪化させる原因となります。
こうしたことから、仮面うつ病の予防、あるいは症状の緩和という意味で、糖分や肉類などを摂り過ぎないようにするということは有効であるということができます。
まとめ
仮面うつ病の知識まとめ、症状・原因・対処法
仮面うつ病の症状8選
・自律神経の不調
・消化器系症状
・呼吸障害
・耳鳴り
・物忘れ
・微熱
・性機能障害
・思考障害・不眠
仮面うつ病の原因3選
・性格
・何らかの出来事
・さまざまなストレス
仮面うつ病の対処法5選
・薬物療法
・カウンセリング
・鍼灸治療
・漢方療法
・食べ物を変える
いかがでしたか?
「仮面うつ病」というのは一般的にはまだ知名度のない言葉ではありますが、いくらかの理解を深めていただくことができたのではないかと思います。
もし、ご自身や知人にこのような症状がある場合は、症状が深刻化する前にいち早く対処法を試してください。


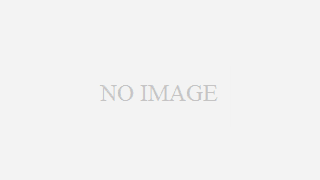





















コメント コメントが多い記事もあります。読んでみるとモチベーションアップに繋がります。