これまでの人生で一度も「目標」を立てたことがないという人はほとんどいないと思います。
しかしその目標を、本当に満足行く形で達成することができた人は、少ないのではないでしょうか。むしろどちらかと言えば、目標達成に失敗をしてしまった人の方が大多数かもしれません。
実はこの目標達成できる人と、失敗してしまう人との間には、性格や思考パターン、あるいは習慣など、その人の「内面的な部分」で大きな違いがあります。
そこでこの記事では、目標達成する人と失敗する人の違いについてお伝えします。あなたに足りない部分を見つけながら、目標達成できる人を目指してみましょう。
目標達成できる人と失敗する人の決定的な違い14の秘密
課題を「自分のもの」として考えるか、「他人のもの」として考えるか
目標達成には必ず何らかの「課題」が存在します。
目標達成ができる人は、この課題を「自分のもの」として考えますが、失敗する人はこの課題を「他人のもの」として考えます。
具体的に言うと、「できる人」はその課題やクリアすることをすべて自分の責任であると考え、その実現のために最大限の努力をします。
一方で「できない人」は、その課題を他人(会社や学校、親など)から押し付けられたものであると考えたり、その実現を誰か(もしくは何か)が邪魔をしていると考えます。
そして上手く行かないことがあると、その責任を外部へと帰属させます。
物事を肯定的に捉えるか、否定的に捉えるか
目標達成ができる人は基本的に物事を肯定的に捉えますが、失敗をする人は否定的に捉える傾向があります。
例えば、「コップに半分の水が残っている」場合、目標達成ができる人は「まだ半分も残っている」と考え、できない人の場合には「もう半分しか残っていない」と考えます。
「できる人」は、自分の手元にあるリソース(この場合ではコップ半分の水)をどのように最大限活用するのかを考えますが、「できない人」は現状に失望し物事を諦めてしまうのです。
物事を肯定的に考えるのか否定的に考えるのかという違いは、ある程度遺伝子によってプログラムされているということが知られています。
また、同時に幼少期から青少年期に過ごした環境もこの思考パターンに大きな影響をもたらします。
一般的に幼少期から周囲の人々に肯定される経験が多く、自己肯定感が高く育った人は周囲の物事もまた肯定的に見る傾向が強くなります。
逆に周囲に否定される経験が多く、自己肯定感が低く育った人は否定的に物事を見る傾向になります。
自分を信じることができるか否か
先ほどの「物事を肯定的に捉えるか、否定的に捉えるか」とも強く関連するのですが、目標達成ができる人は自分を信じる力(自信)が強く、失敗する人はその力が弱い傾向にあります。
目標達成の過程で何らかの困難に直面したとき、「できる人」は「自分はこの困難を乗り越えられる」と信じて行動をするのに対し、「できない人」は自分の力を信じることができずに諦めてしまいます。
また、自分を信じることができない人は失敗に対する恐れが強く、失敗によって今あるものを失うリスクを真っ先に考えてしまうため、そもそも「目標」にチャレンジをすることを避けることが多くなります。
自己中心的か他者中心的か
目標達成ができる人はあらゆることを自己中心的に考えますが、失敗してしまう人は他者中心的に物事を考えます。
ここで言う「自己中心・他者中心」とは必ずしも「利己的・利他的」という意味ではなく、価値判断や行動の基準を「自分」に置いているか、もしくは相手や世間、社会などの「他者」に置いているかどうかの違いを指します。
自己中心的な「できる人」は、「他人からどう思われるのか」ではなく「自分はどうしたいのか」という感情に基づいて行動するため、人目を気にすること無く行動します。
もちろんそのことについて他人からどう言われたり、思われようと気にしません。
一方で他者中心的な「できない人」は、「他人からどう思われるのか」が大変気になり、なかなか行動を起こすことができません。
行動を起こしたとしても、周囲から止められたり仲間外れにされそうになった場合にはあっさりと諦めてしまいます。
また、自己中心的な人は自己承認欲求が低く、他者中心的な人ほど承認欲求が高いという違いもあります。
自己中心的な人は「自分を承認するのは自分だけで良い」という唯我独尊的な傾向があるのに対し、他者中心的な人は絶えず周囲からの承認を求め、「自分の背中を誰かに押して欲しい」と考える傾向があります。
スキルの上昇を見込めるか否か
目標達成ができる人は、今の自分が持っているスキルはこれからもっと上達していくものと考えます。
一方で失敗してしまう人は、今の自分のスキルが限界だと考え、今持っているスキルだけで目標達成をしなければならないと考えます。
「できる人」はスキルを今後さらに上がっていくものと考えるため、それを上げるための努力を惜しみません。さらに一つのことを継続してやりぬく粘り強さも持っています。
そうした結果として、実際にスキルを上達させて成功のための強力な武器とします。
しかし「できない人」は、スキルが伸びるという期待を見込んでいないため、努力をせず、また継続力もあまりないため結果としてほとんど上達をしていきません。
自分の個性を理解しているか否か
目標達成ができる人は、自分がどのような個性の持ち主なのかをしっかりと理解をしています。失敗してしまう人は、全く理解していないか、理解していたとしても不十分である傾向があります。
人はそれぞれ持つ個性によって、「向いていること」「向いていないこと」が存在します。
「できる人」は、自分の向いていることを理解しており、それに基づいて目標設定やそのためのアプローチの選択を行うため、行動に無駄がありません。
最低限の努力で最大限の結果を引き出すことができるのです。
そして、結果が出た分だけ「努力をすれば必ず成果を出すことができる」という確信(思い込み)を強めていくため、より努力をするようになっていきます。
一方で「できない人」は、自分の個性を把握しておらず、見当違いな方向に努力をしてしまうことが多々あります。
その結果として「努力をしているのに、全然成果が上がらない」という「失敗体験」を多く積んでしまい、無気力状態になり努力することを諦めていってしまいます。
ちなみに「物事を肯定的に捉えるか、否定的に捉えるか」で紹介した「自己肯定感」は、自分の個性の理解することにおいても重要な役割を持ちます。
幼少期から自分の個性を承認されてきた人は迷いなくその個性を伸ばしていくことができます。
しかし、個性を承認されなかったり、あるいは否定されたりして育ってきた人は、その個性に確信を持つことができず、一体何をすれば良いのかがわからないまま人生の貴重な時間や労力を浪費していってしまいます。
他者を頼るか、自分の力でやろうとするか
少々意外ではありますが、目標達成ができる人は積極的に周囲の人々に頼ろうとし、必要とあれば助けを求めます。一方で失敗してしまう人はあらゆることを自分一人の力だけで行おうとします。
「できる人」は自分の個性や強みを理解している反面、自分の不得意な部分や弱い部分もしっかりと把握をしています。
そのため、不得意な部分はそれを強みとしている他人に頼ることで、時間や労力を無駄遣いしないようにします。
逆に「できない人」の場合、自分の個性をしっかりと把握していないため、不得意な部分や弱い部分を「○○ができないのは自分のせいだ」と考え、すべて自分の力だけでカバーしようとします。
その結果として無駄な時間や労力を積み上げてしまい、成果もあまり上がらない状態に陥ってしまいます。
行動をするのが早いか、遅いか
目標達成ができる人は何においても行動が早いです。逆に失敗してしまう人は行動を起こすのが遅いと言えるでしょう。
「できる人」は、興味を持ったことや、やるべことに対してすぐにそれを行動に移します。行動をしながら物事を学んでいき、成果や反省点を振り返り、それらを次の行動へと反映させていきます。
しかし「できない人」は、まず興味や関心のセンサー感度が低く、行動を始めるのが遅い傾向があります。
また、興味を持ったことがあってもすぐには行動に移さず、万全な状態となるまで準備をしてから始めようとしますが、そうこうしている内に状況が変化をしていき、結局何も行動をすることができずに終わってしまいます。
リスクを取るか否か
目標達成ができる人はリスクを踏まえた上で行動を起こしますが、失敗してしまう人はリスクを恐れるあまり行動を起こさないまま終わります。
あらゆる物事には何らかのリスクが存在します。特にまだ一度も達成したことのない目標は、かなり大きなリスクを背負う可能性が高いです。
「できる人」はそうしたリスクをしっかりと認識した上で、どうにかして最小化することができないかと考えを巡らせます。
一方で「できない人」はリスクの存在そのものを忌避しようとするため、新しい目標にチャレンジすることができません。
闇雲に努力をするか、効率化するか
目標達成のためには努力をすることは不可欠です。
ただし「自分の個性を理解しているか否か」や「他者を頼るか、自分の力でやろうとするか」でも述べたように、効果が上がらなかったり、多くの時間や労力を必要とする努力は、ときに目標達成を阻害する要因ともなってしまいます。
こうしたことを踏まえ目標達成が「できる人」は、無駄な努力をしなくても済むように、さまざまな作業を効率的に行うようにします。
一方で「できない人」はあらゆることを努力してこなそうとし、結果として心身が疲弊し挫折をしてしまいます。
効率化とは具体的には、仕事や勉強がやりやすいようにリフォームや模様替えをしたり、資料や教材をPDFや電子書籍などのデジタルデータとして保管して持ち歩いたりすることを指します。
また移動時間やトイレ中など、空いた時間を利用して勉強をしたりすることもそれに当たります。
効率化ができない人は、不便な環境で仕事や勉強をしたり、しっかりと机に向かってまとまった時間を確保しなくてはダメだと思い込むことよって、結果として多くの時間や労力を無駄にしているのです。
新しい情報をインプットするか否か
目標達成ができる人は、絶えず新しい情報を自らにインプットしていき、自分自身をアップデートしていきます。
一方で失敗してしまう人は、そうした意欲があまり高くなく、ある程度の知識やスキルが身に付いたらその時点で満足をしてしまう傾向があります。
どんな分野においても、目標達成をして成功する人というのは好奇心が強く、物知りであったり一芸に秀でている人が多いです。
また、そのような人に共通するのは、必ずしも「目標達成をする」「成功する」ことを目的としておらず、楽しみながら自然と勉強や努力をしています。
新しい情報をインプットし、自らをアップデートする最も手っ取り早い方法は読書です。自分で読む本を選び、自らの意志で読み進めていくことで、主体的に情報を取得していくことができます。
さらにインターネットも使い方によってはこの読書と同じような効果を発揮することができるでしょう。
目標達成までをプロセスとして管理できるか否か
目標設定について書かれた自己啓発本を読むと、「自分の達成できる範囲の目標を立てる」と提案していることが多いです。
これは確かに「目標を達成する」という意味では効果的であると言えますが、その一方で「それが本当に自分のやりたかったことなのか?」という根本的な問題を孕んでいます。
こうしたことから目標設定をする際には、「小さな目標」ではなくいっそのこと「大きな目標」を立てたほうが良いのも確かです。
しかし、「大きな目標」を立てたときに、それが単なる「夢」や「願望」で終わってしまうリスクも高いとも言えます。
そこで重要なのが目標達成までの道のりを「プロセス」として管理するということです。
目標達成ができる人には、この「プロセスとしての管理」ができる人が多く、失敗する人は目標達成のプロセスまで考えていない傾向があります。
「プロセスとしての管理」とは具体的には、大きな目標を複数の小さな目標に分割して管理するということです。
例えば年間100万円貯金をするという「大きな目標」を立てた場合、毎月あたり8万5千円を貯金するという「小さな目標」を立てて、それをクリアしていけば目標達成をすることが可能となります。
また、このように目標を分割化することは「何時までに何をやらなければならないのか」というように目標を明確化することにも繋がります。
そのときそのときで具体的に何をやるかがハッキリしているため、時間やエネルギーを無駄なく効率的に使うことができるようになります。
プラスのインセンティブで行動するか、マイナスで行動するか
人を含めた動物が行動をする際、その行動はインセンティブ(動機付け)に基づいて行われます。そしてそのインセンティブはプラスのものと、マイナスのものの二種類に分けることができます。
プラスのインセンティブとは、それを実現することでより大きな快楽にありつけたり、自分の存在をより高めたりする動機付けを指し、基本的に「〜したい」という感情に基づきます。
一方でマイナスのインセンティブとは、それを実現することによって恐怖や不安などのマイナスの感情から逃れる動機付けを指し、基本的に「〜したくない」という感情に基づきます。
例えば「動物が食べ物を求めて探しまわる」場合、「美味しいものが食べ『たい』」という気持ちで行動するのがプラスのインセンティブで、「飢え死に『たくない』」という気持ちで行動をするのがマイナスのインセンティブになります。
目標達成において成功する人は、プラスのインセンティブに基づいて行動しますが、失敗してしまう人はマイナスのインセンティブに基づいて行動する傾向があります。
基本的に「〜したい」というプラスの感情には際限がないため、それに向かってどこまでも努力や工夫をしていくことができます。
逆に「〜したくない」というマイナスの感情は、そこから逃れることができれば目標自体が消えてしまうため、それ以上の努力や工夫をすることができないのです。
「究極の理念」を持っているか否か
目標達成できる人は損得勘定を抜きにして自分の中にある「究極の理念」に基づいて行動をします。一方で失敗してしまう人は損得勘定に基づいて行動をしようとします。
「究極の理念」とは、自分の人生全体を象徴できる目標のことです。そこにはその人の美学や価値観などが反映されています。
こうした理念を持っている「できる人」は、それについて考えるだけでワクワクしてしまい、居ても立ってもいられずに行動を起こすのです。
一方でそれを自覚することが「できない人」は、「自分が損をしないこと」を最重要視しているため、なかなか行動することができず、行動を起こしたとしても一貫性がなくなってしまう傾向があります。
まとめ
目標達成できる人と失敗する人の決定的な違い14の秘密
・課題を「自分のもの」として考えるか、「他人のもの」として考えるか
・物事を肯定的に捉えるか、否定的に捉えるか
・自分を信じることができるか否か
・自己中心的か他者中心的か
・スキルの上昇を見込めるか否か
・自分の個性を理解しているか否か
・他者を頼るか、自分の力でやろうとするか
・行動をするのが早いか、遅いか
・リスクを取るか否か
・闇雲に努力をするか、効率化するか
・新しい情報をインプットするか否か
・目標達成までをプロセスとして管理できるか否か
・プラスのインセンティブで行動するか、マイナスで行動するか
・「究極の理念」を持っているか否か
あなたは目標達成できる人か、それとも失敗してしまう人か、どちらの特徴に近かったでしょうか。
もし失敗してしまう方に近いなら、今からでも目標達成ができる人に近づいていけるよう、生活や思考の習慣を変化させていきましょう。


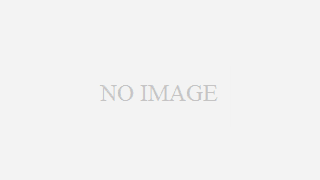

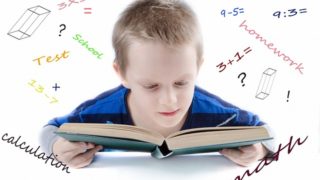























コメント コメントが多い記事もあります。読んでみるとモチベーションアップに繋がります。